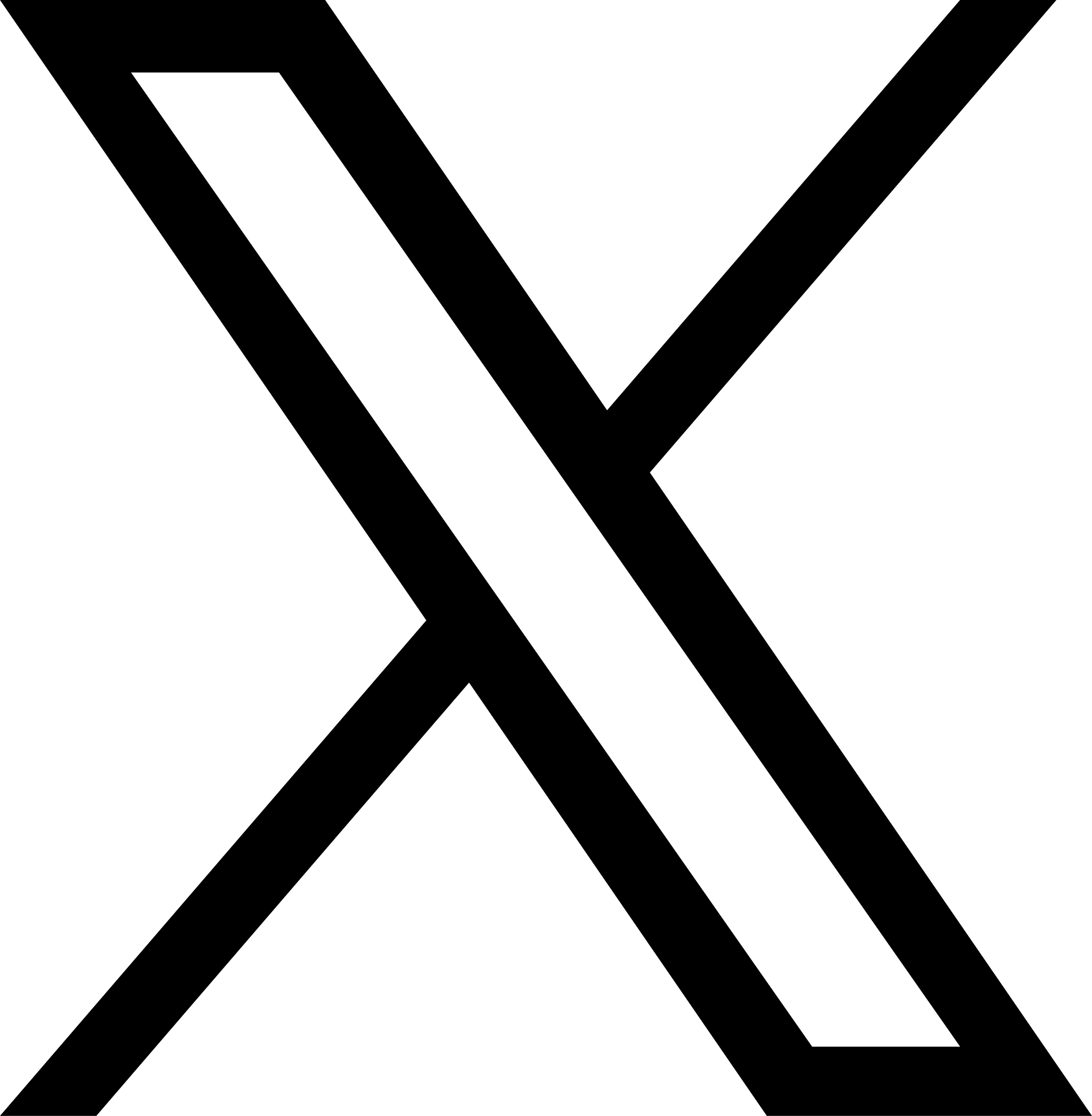こんにちは。広報ユイカです!
harmoでは、患者さまの声や困りごとを聴き、患者さまの声に寄り添った電子お薬手帳を作りたいと思っています。そして、患者さまのリアルな声を医療へお返しするという取り組みを実現したいと思っています。その第一歩として、様々な疾患を抱える患者さまにご協力いただき、ご意見をいただく取り組みを開始しました!
✔疾患のきっかけや経緯
✔疾患とともに生きること
✔お薬についての課題
などをお聞きし、harmoは患者さまの声に寄り添いながら、患者さまと一緒に電子お薬手帳を作っていきたいと思っています。そして、疾患と共に生きる方が少しでも生きやすい世の中を目指しています。ぜひ、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
今回お話いただくのは、産業看護師として企業で働く川畑美香さんです。
2019年のケガをきっかけに、慢性の上肢障害となり毎日の内服が欠かせない生活になりました。
「看護師として患者さんを理解しているつもりだった」と語る川畑さん。
自分自身が疾患とともに生きる当事者となったからこそ感じた苦悩や葛藤があったといいます。
看護師として母として、明るく前向きな川畑さんに、障がいに向き合えるようになった経緯と日々の服薬管理などの大変さや工夫をお聞きしました。
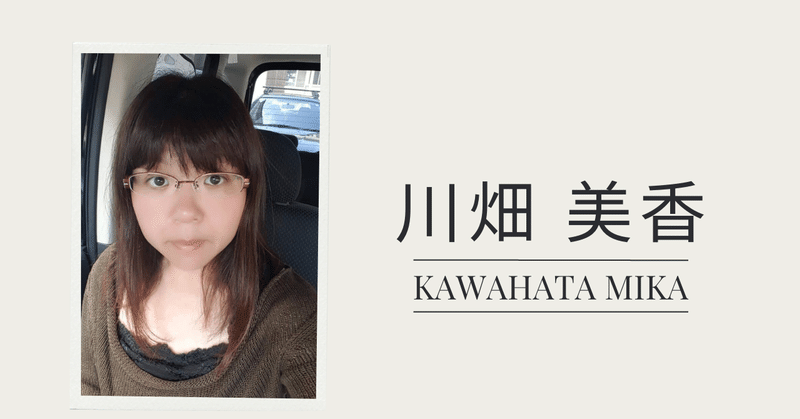
周囲の優しさが負担に。疾患を受け止めることの大変さを体感
―――疾患のきっかけや経緯についてお話しいただけますか?
川畑さん
現在、手首に障害があって日常的に装具を装着して生活しています。
はじまりは、2019年にスキーで転倒し手首を痛めたのがきっかけでした。
最初は骨折した右手だけが不自由だったのですが、利き手だった右手を補うために、普段使用しない左手を酷使してしまったことで左手も負傷してしまいました。結局、左手にも障害が残り現在に至ります。
当初から、整形外科を受診していましたが、地域柄「手」を専門にしている病院があまりなかったんです。
始まりが「手のケガ」だったので、私自身もいつか治ると思っていました。
自身が看護師なので、ケガのあとの大まかな経過も予想できていましたしね。
しかし思ったようには治らず、周囲の人からも「まだ治らないの?」とか「医師の技術が悪いんじゃないか?」とかいろいろと言われるようになったんです。もちろん、知人や同僚などは私の状態を心配して言ってくれている、ということは理解していましたが、自分自身も治らないことへの不安や焦りが大きくなっていたので、周囲からの助言を素直に受け止められませんでした。
また、痛み止めを常用することに対しても「痛み止めに依存しない方がいい」とか「もっと強い薬が必要になってしまうよ」などということを言われるようになり、実際に服用を辞めてしまったこともあります。でも、薬を飲まなければ症状は悪化しますから結局薬を再開することになる。
自分の体のことすらコントロールできない自分が嫌でしたし、まわりに色々と言われることで精神的にも追い詰められてしまって、殻に閉じこもるような生活をしていた時期もありました。

疾患とともに生きることを前向きに捉えるまで
この疾患と向き合う前は、いわゆる“普通”の身体機能が当たり前に揃っていました。
健常者、障がい者、という呼び方は好きではありませんが、今あえて言うならば、健常者は身体機能が全て揃っている人で、障がい者は身体機能が全て揃っていなくても生活できている人、だと思っています。
もちろん、最初からそのように考えられたのではありません。
「できない」という部分に注目しがちで、できなくなったことに対する葛藤を経験する時期も長く続きましたし、その時期を乗り越えたからこそ感じるようになった感情です。
障害や疾患そのものは「良いこと」ではないかも知れませんが、疾患を抱えなければ見えなかったこともたくさんあります。いろいろな人との出会いもあって、そこから学び成長できたという感覚はありますね。
それまでは「看護師として」障害や疾患をかかえながら生きる患者さんのことを理解してきたつもりでしたが、ケガをきっかけに「当事者」になりました。そこで気づいたのは「障害や疾患とともに生きること」に対して理解したつもりでいただけだった、ということ。看護師としての鼻をへし折られた感じでした。

大切な人と過ごす日常が生きがい
いろいろありましたが、結局「人」に支えられました。
辛かった時期に、主人がふと「障がいがあってもなくても“自分自身”が変わったわけじゃないのだから、気にしなくても大丈夫なんじゃないか」というようなことを言ったんです。何気ない一言だったと思いますが「自分」は何も変わらない、という当たり前のことに気づかせてくれました。
また、医師からは「治せなくて申し訳ない。でも、頑張ってくれてありがとう」とも言われました。ありがとう、という言葉は私から言うものだと思っていたので、驚いたのと同時に「言葉のありがたさ」を感じましたね。
今の私にとっては、大事な人と穏やかに過ごす日常がなによりも大切で、大事な人と笑って好きなことができる毎日があるから、生きていられるんだと思います。
内服や受診の管理をカンタンに。アプリに期待
多種の薬剤を管理し続けるのは大変です。
現在は朝4種類、夕4種類の薬を内服しています。でも、服薬は欠かせないという現状がありつつも実際はアプリでタイマーをかけていても服薬前にタイマーを止めてしまい、飲み忘れることもあります。薬の飲み忘れは症状悪化につながりますので、タイマーだけでない「飲み忘れを防ぐツール」があったらいいな、と思いますね。
さらに、私は多くの薬剤を飲んでいるので、現在のお薬手帳の不便さも感じています。
普段からお薬手帳を持ち歩く習慣がないので、風邪などで他の医療機関を受診したときに常用薬の情報を医師に伝えるのが大変なんです。家族の受診付き添いのときも紙のお薬手帳を持っていなくて、いざというときに役に立たなかったり。医療機関での薬情をうまく伝えられるツールもあったらウレシイですね。
―――ヘルスケア関連のアプリは使っていますか?
薬の管理や体重の管理など、これまでにもたくさんの管理アプリを使ってきましたが、結局使いこなせたものは少ないです(笑)とくにサブスクのものは使い勝手が悪ければすぐに辞めましたし、広告が出るのも面倒ですしね。
現在はGoogleカレンダーで受診日の管理をしているくらいですが、本当は薬や受診の予約が簡単にできるツールがあったらいいな、と思います。
―――harmoおくすり手帳(※)の機能について意見を聞かせてください。
服薬情報の家族連携機能は便利だと思います。
紙のお薬手帳だと子ども1人に1冊ずつですから、子どもが増えればお薬手帳も増えていきます。急な受診に備えて人数分のお薬手帳を持ち歩くのは大変ですよね。でも、子どもの服薬情報も自分のスマホで管理できれば、一人ひとりのお薬手帳を持ち歩かなくても良いですし、急にかかりつけ医院以外を受診するときも安心。使用中の薬剤を確実に医師に伝えられます。
また、子どもに限らず、家族の受診付き添いのときにも便利だと思います。
例えば、過去に施設に入所している祖母の受診付き添いを頼まれたことがありました。そのときに施設から受け取ったのは『保険証』だけ。同居していないから受診時点での服薬内容はわからないし、内服歴もわからずに困った経験があるんです。
子育てや介護に関わっていれば、今後も家族の薬情が必要になる場面があるかも知れません。私のように自分自身も服薬している場合は、できるだけカンタンに使えるツールがありがたいですね。
harmo、ぜひ使ってみます!

※harmoおくすり手帳(https://service.harmo.biz/okusuritecho/customer/)
スマートフォンアプリや専用のharmoカードを利用し服薬情報を管理することが出来る、電子お薬手帳サービスです。